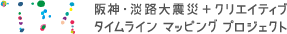南芦屋浜コミュニティ&アート計画
1998年4月原 久子さん/アートプロデューサー、大阪電気通信大学 総合情報学部 教授
テキスト:中野悠(2011.10.05)原 久子さん(アートプロデューサー/大阪電気通信大学 総合情報学部 教授)
京都造形芸術大学勤務を経て、フリーランスのアートプロデューサー、編集者、ライターとして活動されてきた原 久子さん。雑誌・書籍の編集企画、展覧会やアートイベント、ワークショップ等の企画運営にたずさわってこられたほか、地域に根ざした実践的な芸術文化活動について考え、NPOの一員として関わってこられました。2005年からは大阪電気通信大学の総合情報学部教授として、アートマネジメントを教えておられます。原さんが関わられた、震災復興との関係が深いプロジェクトについて、当時から現在までの想いをまじえつつお話をうかがいました。
笑顔が、さらなる笑顔を生みだす
私が関わった「居留地映画館」(※1)は震災復興事業の一環として2001年に開催されました。神戸市からオファーがあり、私もメンバーであるC.A.P.(芸術と計画会議) が企画・制作を担当、さまざまな提案をしていきました。
たとえば「BIG SMILE 2001」は、神戸市立博物館の外壁に2001人の市民の笑顔を大きく投影。幼稚園や企業、個人などいろんな所をまわって撮影、スライドショーにしたものです。約5秒ごとに次の画像が映り、ひととおり見るには数時間かかるのですが、写真に登場した方々はイベント当日に足を運んでくださり、自分や友達の顔を見つけるたびに歓声があがって、さらなる笑顔が生まれるという光景でした。これは取り戻した笑顔を伝えるためのプロジェクトでした。
光と影、街歩き、街や関係性の中に見いだせるもの
私は「スリット・ショー」というプロジェクトを担当しました。居留地内のビルの隙間や外壁などに映像を投影し、街を回遊し見てもらうプログラムでした。
このプログラムの趣旨は、神戸は日本で初めて映画を上映した場所であり、居留地のまち全体を映画館にしたかったということ。たとえば元町なら大丸へ行くためだけに足を運ぶというような「点と点」の移動が多かったため、光と影の風景の中、神戸という街をそぞろ歩いてもらいたいという想いをこめました。「こんなところに、こんなものが!」という体験をしてほしかったのです。
of but season a…
光と影は、実体としてはつかめない。けれど影は、実体がなければ現れないものです。このたびの震災でも思ったのですが、人は建物などの「物」にこだわりすぎている。それよりも都市に映し出した影によって、街全体や関係性の中にさまざまなものを見出していくべきなのではないか。このプロジェクトがそれらを意図的に生みだす装置になれば、と思っていました。
散歩で、思い出すという経験を
プロジェクト自体がまちの復興に直接つながるかどうかより、自分たちがやりたいこと、こうだったらいいなと思うことを実行しました。押しつけることはしたくない。アートに関わる人間が、ふだんは思いつかないようなことを提案し、問題提起という大げさなものではなく「散歩」というスタイルで、わすれていたことをふっと思い出すという体験をしてほしかったのです。
参加アーティストは、兵庫県や神戸の人ばかりではありません。これまでの活動から、おもしろい、ぜひ話をしてほしいと思った方々にお願いしました。
プログラムの名称も、映画や影絵を映す原理や建物の隙間などの設置場所から「じゃあ、スリット・ショーにしよう」といった会話の中で決定しました。南芦屋浜の震災復興住宅のように、建物を建てるものとは別次元のことでした。
新しいコミュニティ作りのために
南芦屋浜の震災復興住宅におけるプロジェクト「南芦屋浜コミュニティ&アート計画」(※3)には、1997年初めくらいからアートディレクターとして関わりました。
当時、仮設住宅は色々な阪神間に点在し、もともとのコミュニティがばらばらになっていました。復興住宅は、長屋のように並ぶ仮設住宅が垂直に立ち上がったもの。仮設住宅では、孤独死の存在をはじめ、精神的に追い詰められていく方がいたり、隣近所の人に声をかけにくかったりとさまざまな問題がすでに起こっていました。
新しいまちができた時、それらの問題にどう対処していけばいいかを考えるために、入居予定者や関心のある方に集まってもらってワークショップを実施しました。建物が建つ前から、会話を活発にしていくためのワークショップを継続的にしかけていたのは、新しいコミュニティをつくるため。集合住宅では、コミュニティは自然発生的には生まれないので、事前にみんなが顔を合わせることで発言しやすい場をつくろうと試みました。また、震災から2、3年たって心の内を吐き出したい人や伝えるタイミングを失った人の心をほぐすことができたり、集えてよかったとみんなが思えるようにしたいという想いがありました。
場や経験をシェアすることの意義
このプロジェクトでは、復興住宅内に恒久的なアートワークをいくつか設置しました。今も目にすることができるそれらのアートワークと共に、ワークショップを継続開催していくことも重要な柱でした。アートのワークショップに限定せず、いろんな「作業」をみんなでおこなうことで、引っ越し後すぐにコミュニティを生みだすきっかけになるものです。
たとえば、アーティストたほりつこ氏は屋外緑地にだんだん畑をイメージした作品を制作して。だんだん畑は日本の原風景のひとつだという考えにもとづく造形的な側面があります。家では、ドアを閉めると隔絶されてしまいます。外へ出た時に、だれかと一緒に水をやったり収穫したものを味わったり、さまざまなできごとをシェアする場、装置としてこの作品が存在すればと思っていました。
生活の一部として機能するアート
南芦屋浜のプロジェクトでは、西宮やHAT神戸のように野外彫刻を置くのではなく、生活の一部として機能するアートプロジェクトにしたい、自分たちの考えるコンセプトを住人に受け入れてほしいと考えていました。
集合住宅がある限り機能していくよう、アートワークのコンセプトやメンテナンス方法をまとめたマニュアルをつくって入居者全員に配布しました。そのうち、入居者が入れ替わり、当初のコンセプトを暮らしのなかに継続的に根づかせるのはとても難しいことです。
私たちはこの場所をよくしていきたいと思い、傲慢な気持ちを持たないように努めながらプロジェクトに取り組みました。当時は先駆的な例として、外部からも注目されました。
課題は継続性、キーマンの存在
けれど今、振り返ってみると継続性に大きな課題が残りました。1年後くらいまでは頻繁にワークショップをおこないましたが、住人全員が同じテンションで活動を維持しくのは難しく、外部から仕掛け人がやって来るからするという面がありました。住民の平均年齢は65歳以上、日々の生活に精一杯という方も多かったのです。
また、復興住宅そのものの管理担当者が変わってしまい、アートワークの管理方法が受け継がれないなど、複雑な事情もからんできました。自分がそこに住みつき、言葉を発することのできる立場であれば、もっと違うことができたのかもしれません。
活動を継続し、関係性を保つためには、継続的にコンタクトをとる人物が必要だとわかりました。人を介さなくなると、アートワーク自体の意味合いも風化してしまいます。このプロジェクトが機能していくには、やはり“人”が必要だったのです。
反省から生まれる、これから
この経験を反省するだけに終わらせず、次にどう生かしていくかが重要です。このプロジェクトは復興事業計画に組みこまれていましたが、復興予算のウエイトをハード面に大きく設定するより、それらの一部をマネジメント経費にあてることも可能です。大規模なハード面の整備が本当に必要なのかは、振り返ってみると少し疑問です。ハード面の整備には巨額の予算が必要ですが、同じ額でソフト運営であればより多くのことができるのです。
もちろん、「場」をつくることは必要です。建物をつくることに反対しているわけではありません。「場」をつくったうえで人を育てることや体験をつくること、活動を継続することにも注力するなど、人々の中に残り、これからにつながるものにも同時に投資していくことが重要なのではないでしょうか。
※1 居留地映画館 http://www.cap-kobe.com/eigakan/
※2 C.A.P.(芸術と計画会議) http://www.cap-kobe.com/
※3 南芦屋浜コミュニティ&アート計画 http://skb.ne.jp/maca/home.html