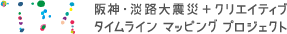『阪神大震災は演劇を変えるか』
1995年12月30日「阪神大震災は演劇を変えるか」出版の経緯
テキスト:九鬼葉子/演劇評論家<前提として-当時の私の状況>
1995年1月17日、私は東京にいた。何年も旅行をしたことのなかった私の、本当に久しぶりの外泊だった。もし家にいたら、半壊となった我が家にいて、大けがをするところだった。全くの偶然により、九死に一生を得た。我が家は、灘区のJR六甲道駅近く。最被災地の一つだ。
東京で震災報道を見て、私が真っ先に考えたことは、まず「今こそ、演劇は人々を救うんだ」ということ。そして本当に恥ずかしいことだが「帰ったら、被災地の写真を撮ろう」というものだった。愚かなことに、「うつるんです」まで買った。痛みを知らぬ者が考えがちのことだ。実際、被災地に帰ると、被災地以外からやってきた「被災地見学ツアー」の面々が大勢、カメラをぱちぱち撮りながら、うろうろしていた。我が家の中までのぞかれ、私達は無神経な眼差しにさらされた。
母からの電話で「食べ物がない。しばらく東京にいるように」という指示を受け、1週間ほど東京に滞在してから帰った。
そして帰宅。そこで見たものは…一言では言えない。思い出すだけでもつらい。とにかく、残酷過ぎて、写真などとても写せるものでないことだけは、すぐにわかった。被災地以外にいる者との温度差を実感した。神戸育ちの私をして、東京にいて、写真を撮ろうなどと、のんきなことを考えたのだから…。
しかし、私には現実が待っていた。演劇専門誌「シアターアーツ」の劇評の締め切りだ。確か1月19日位が締め切りだったが、出版社にぎりぎりまで待ってもらう約束をした。しかし…書けない。まず物理的理由。毎日自衛隊の駐屯地まで水をもらいに行って運ぶのが私の仕事。水は、重い。それ以外にも肉体労働が多く、慣れない仕事で筋肉が痛み、体が1日中だるくて、1日中眠かった。何も考えられない。また、半壊になった家の使える部屋で、家族全員が一緒に寝起きし生活していたため、1人になれる時間もなかった。そして、精神的理由。毎日水を運ぶ際、必ず通る、近所の全壊した家々。そこでは多くの人が亡くなられている。全壊した家の前を通るたび、涙が止まらない。さらに追い打ちをかけたのが、私の演劇に対する不信感。「何も救えないではないか。一体演劇に何ができると言うのか」という疑い。私自身、全く芝居を見たいとも思わなかった。必要なものは、水、食べ物、電気、ガス、清潔なトイレ、風呂だ。
演劇の力に疑いを持った者には、演劇について書くことができない。
何度電話の前に行き、出版社に電話をして「すみません、今回は私の原稿を落としてください」と言おうとしたことか。深い葛藤の中にいた。つらかった。
しかし、私は書いた。なぜ書けたのか、未だにわからない。おそらく「今のこの迷いをそのまま書こう」と思い立ったこと。そして「生きていこう」と思ったことだろう。被災地で生活していて、最初のころは「何故私なんかが生き残ってしまったのだろう」と、自分の生に疑いを持った。後で聞いたところによると、それは被災者心理らしい。助かった直後はテンションが上がるが、その後で、ど~んと気持ちが落ちるものらしい。亡くなった方が周囲にあまりにも多く、「絶対生きているべきだったあの方が亡くなられて、私みたいな者がなぜ生き残ってしまったのだろう」と考えてしまうものらしい。自分など生きる価値がない人間だ、とまで自己評価が下がってしまうのだ。
しばらくぬぐい去れなかったその思い。そんな気持ちから、なんとか立ち直れたらしい。「生きていこう」と思えたのだ。
その時の原稿が「シアターアーツ」2号、「死線を越えて―神戸復興への願いを込め…」である。
まず、その原稿が、私の出発点となった。
<出版のいきさつ>
阪神・淡路大震災を機に、演劇は変わるかもしれない、という予感があった。
1980年代の演劇は、戦争も学生運動も終わり、バブル景気に沸き、一見平和に見える時代の中で、一見明るい笑いに満ちたものが多かった。しかし、その裏には、「何かが起きる寸前」の、見えない不安が深く潜行しているようにも思えた。
そして1995年に起きた阪神・淡路大震災と、地下鉄サリン事件。その両方の事件は、いつまでも続くと思っていた日常に、ある日突然非日常がなだれ込んでくることを実感させた。日常と非日常は、薄皮一枚の差しかないのだ。
新しい時代感覚が生まれるかもしれない。そんなことを、演劇評論家の内田洋一氏や瀬戸宏氏らと話すうち、演劇の観点から震災を記録しようと言うことになり、「阪神大震災は演劇を変えるか」が生まれた。
(内田氏や瀬戸氏は、別の見解ももっているかもしれないが、私はそう思って出版した)。